

メンバーは本願寺僧侶その他数名
本願寺との歴史的対立
故意に悪印象を与えている
親鸞会を攻撃的と思わせたい
親鸞会これが『非オープン』?
意図的な誇張と極端な飛躍
根拠なき推測と憶測を繰り返す
具体性はないまま「危険だ」
調査で実体がないことが明らかに
悪意と偏見から平気で「カルト集団」呼ばわりする寺報配布
鳥取県の本願寺末寺K寺とJ寺
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり葬式法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールしても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトでない
内容には全く触れられていません。よほど読ませたくないのでしょう。
正しい教えに従うのが悪い?
母から親鸞会に誘われて
死が怖くなる
親鸞会の会員となり仏法を続けて聞いております。
批判者も、もっと親鸞聖人の教えを真摯に学んでもらいたい。
人生の切実な問いに答えるのは司法でも多数決でもない。
親鸞会で初めて知った、龍谷大学でも聞けなかったこと
真実を求める道のりも、思考停止してはすすめない
世間からも批判されている本願寺が教義を正し立て直しを計ろうとする健気な努力
本願寺の本尊についての現状
これでは門徒がお気の毒。
旧態依然の真宗大谷派だった。
今後も教えが説かれなければ、本願寺の崩壊はもう時間の問題
東本願寺、西本願寺の迷走
何のための医療施設?
後継者不足に悩む末寺
御正忌法要の惨状
「宗制」に本願寺が「名号本尊」を明示せざるをえなくなった
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
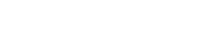
中外日報(平成19年11月6日号)に、本願寺派のビハーラ活動が20周年を迎え、本願寺派大谷光真門主の�お言葉�が報道されていました。
ビハーラ活動とは、どういうものか。
仏教をもととした、全人的ケアを目指した活動だそうです。
ビハーラ活動は、生死にかかわる深いいのちのうめきを受けとめます。国際保健機関(WHO)は、全人的ケアの一つとして、患者と家族の宗教的苦痛をケアすることを公式に採択しました。その宗教的苦痛(スピリチュアル・ペインの訳語。実存的苦痛、霊的苦痛とも訳される)とは、「どうして私は死ななければならないの」「私の人生の意味は何だったのか」「死んだら私はどうなるの」「死にたい」など、まさに本人のいのちの根本にかかわる深い苦しみです。日本でも、このような患者と家族の宗教的な苦痛に応えることが宗教者に求められています。
(本願寺伝社会部・ビハーラ活動の方向性)
「死んだら私はどうなるの」「私の人生の意味は何だったのか」は、全ての人が抱えている重大な問題です。
この問題を解決するための活動ですから、大変意義深いことと思います。
では、この問題に20年間取り組んできたという本願寺派大谷光真門主は、どのように言っているでしょうか。
仏教の根本は生死を超える悟りを開くことであり、浄土真宗はそれを往生成仏という教えで受け止めています。生死の悩みを切実に抱えていらっしゃる方々とともに歩み、その気持ちをどのように受け止め、どのようにしてそれを乗り越えていくかということは誠に大事なことだと思います。(中外日報)
そして、浄土真宗の教えについて、次のように語っています。
み教えに遇ってその悩みを転換してゆくことができれば誠に素晴らしいことでありますが、そこまでいかなくても、ともに寄り添っているだけでも大きな意味があると思います。何もできないということがあっても、阿弥陀さまのお慈悲の中でともに過ごしている貴重な時間であると思います。(同)
「寄り添っているだけでも」とか「何もできないということがあっても」と、ずいぶん弱気な発言が続きます。
最初に紹介した、宗教的苦痛に答え、解決しようという熱意が、どうも感じられません。むしろ、「死んだらどうなるのか」「人生の意味は何だったのか」には、門主さんも分からないからとても答えられないので、せめて不安を和らげようといった、精神ケアで止まっているのではないかと思われます。仏教の根本の「生死を超える悟りを開く」や浄土真宗でいう「往生成仏」は、絵に描いた餅なのでしょうか。
苦しみ悩む人に寄り添ったり、励ますことも、もちろん大事なことですが、それだけで終わるのが、仏教ではないはずです。
仮に精神をケアをしようとしても、刻々と死が迫っている人、今臨終という人に、どんな励ましの言葉をかけることができるでしょう。そんな一時の気休めではなく、どうしたら、その人の苦しみを本当に救うことができるのかが、仏法には教えられているはずです。今死なねばならない人にとっては、この生死の一大事こそが大問題なのですから。
その苦しみを根本から解決する、しかも一念(あっという間もない極めて短い時間)で救うというのが、阿弥陀仏の本願です。
如来の大悲、短命の根機を本としたまえり。もし、多念をもって本願とせば、いのち一刹那につづまる無常迅速の機、いかでか本願に乗ずべきや。されば真宗の肝要、一念往生をもって淵源とす(『口伝鈔』)
「弥陀の悲願は徹底しているから、一刹那に臨終の迫っている、最悪の人を眼目とされている。もしあと一秒しか命のない人に、三秒かかるようでは救えない。一念の救いこそが、弥陀の本願(誓願)の主眼であり、本領なのだ」と覚如上人は教えられています。
弥陀の救いは一念で成就するのですから、手遅れの人は一人もいないのです。
しかも、この一念の救いは、弥陀の本願にしかない最も大事な特長ですから、「真宗の肝要、一念往生をもって淵源とす」とまで断言されているのです。
ところが、現在の本願寺は、この一念の救いをまったく説いていません。聞いたことも、読んだこともありません。浄土真宗の肝要「一念往生」が、まったく抜けているのです。浄土真宗の教団である、本願寺派が存在する目的は、親鸞聖人があきらかにされた、阿弥陀仏の本願、一念の救いを、全ての人にお伝えすること以外にないはず。ビハーラ活動は、その目的を果たすための、手段です。苦しみ悩む人によりそうのも、弥陀の救いにあわせるためではないのでしょうか。
ビハーラ活動が 「阿弥陀さまのお慈悲の中でともに過ごしている」、死ねば極楽へいけるのだから、今の苦しみにも耐えていきましょうと、苦しむ人を一時的に慰めることが目的になっているのは、一念の救いを伝えるという大切な目的が分からないからです。門主自身が、まったく分かっていないからではないでしょうか。
蓮如上人は、死んで弥陀の極楽浄土へ往生できる人は、どんな人か、次のように教えられています。
一念の信心定まらん輩は、十人は十人ながら百人は百人ながら、みな浄土に往生すべき事、更に疑なし。(『御文章』)
誰でも、死ねば極楽へいけるのではありません。一念で弥陀に救われた人だけが、十人も百人も、みな浄土に往生できると言われています。
阿弥陀仏の救いは、一念往生、現在ただ今ハッキリいたします。そのために人は生きる、どんなに苦しくても生きねばならないのは、この弥陀の一念の救済にあう為なのです。ですから、どんな病気の人も、肉体がつらい思いをされている方でも、この一念往生の弥陀の本願を聞けば、必ず救われます。ただ慰める活動ならば、本願寺でなくても、いろいろなNPOや、ボランティア団体がやっていること。仏法の目的を、決して忘れてはなりません。
平成20年4月には、特別養護老人ホーム「ビハーラ本願寺」と、緩和ケア病棟を備えた「あそか第2診療所」が本願寺所有地に完成するといいます。
弥陀の本願を、正しく伝えるためのビハーラ活動なら、大変素晴らしいことですが、そうでないなら、何のための医療施設なのでしょうか。悩み苦しむ人たちの心を根本解決する施設になってもらいたいと、切に願っています。