
親鸞会と本願寺の相違点
浄土真宗の正しい御本尊は?
×木像でも絵像でもよい
○御名号でなければならぬ
阿弥陀仏の救いについて
×ハッキリするものではない
○救われたら、 ハッキリする
助かるのはいつか
×死なねば助からぬ
○生きている時に助かる
救われたらどうなるのか
×この世で救われたということはありえない
○無碍の一道、絶対の幸福になれる
どうしたら助かるのか
×念仏さえ称えておればいい
○真実の信心一つで救われる
喜んでいること
×死んだらお助けを喜べ
○現在、助かったことを喜ぶ身になれ
念仏について
×念仏はみな同じだ
○自力の念仏では助からぬ。
他力の念仏を称える身になれ
使命としていること
×葬式・法事・読経・遺骨の後始末
○本当の親鸞聖人の教えを伝えること
マンガで分かる
親鸞会と本願寺の違い
作者へメール
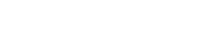
第2の非難 諸善は、獲信の因縁ならず
(4)「諸善も獲信の因縁」の、文証を求める本願寺
親鸞会・文証で開顕する
真実開顕を急ぐ親鸞会は、不毛な論議はしておれぬ。
早速、求めに応えて、文証で、修善も獲信の因縁(宿善)になる真実を開顕することにしよう。
〝修善をすすめた文証など、あろうはずがない〟と、タンカを切られる本願寺サン、弥陀の19願文や、釈尊の『観経』の教説を、どうお読みになっているのだろう。
本師本仏の阿弥陀仏には、48のお約束がある。世に名高い、弥陀の48願といわれるものだ。
その中に「あらゆる人を救いとる」と誓い給うた願が、3つある。18・19・20の三願だ。
「どんな人をも、必ず絶対の幸福に救う」の18願は、自らの本心に随って誓われたもの。随自意の願とか、王本願とかいわれるのは、そのためである。
なにしろ、自惚れ強く、相対の幸福しか知らない我々を、絶対の幸福まで導くことは、難中の難事。どうしても、善巧方便が不可欠だった。
19・20の2願は、その必要に応じて建立なされたものである。
18願、絶対界へ導くために、一時、我々の意に随って誓われたものだから、19・20は、随他意の願といわれる。
自惚れ強く、どうしても自力の執着離れ切れず、流転を重ねる我々に、実行できるだけやってみよ、気の済むまでやってみよ(19・20の随他意の願)。
できないときに、できないままを、無条件で救いとる(18の随自意の願)というのが、弥陀の正意なのだ。
随自意、真実の願に誘引するための、随他意、方便の願だから、三願は孤立したものでないことは、明白である。弥陀が、もし18願のみで救済できるなら、方便2願を建てられるはずがない。
本願寺〝本願を知らず〟では困るのだ
では、その19の誓いを聞いてみよう。
「設ひ、我仏を得んに、十方の衆生、菩提心を発し、諸の功徳を修し、至心に発願して、我が国に生れんと欲はん。寿終るの時に臨みて、たとひ大衆と圍繞して、其の人の前に現ぜずば、正覚を取らじ」
やさしく、解説すると、次のようになる。
〝たとい私(法蔵菩薩)が、仏になりましても、十方の人々が、人生の苦しみの連続に驚いて、どうしたら平和な安楽な世界に、生まれることができようか。
それには、悪を慎み善を励まなければならぬ、と奮発心をおこし、あらゆる善を一生懸命実行して、その力で、我国(浄土)に生まれたいと願う者は、臨終に、諸仏菩薩にとりまかれて迎えにゆこう〟
「諸の功徳を修し」とは、諸善万行、善と名のつくものなら何でも実行しなさい。
知っただけでは観念の遊戯、論語読みの論語知らず、になってしまう、実行しなければ善果は得られぬ。
〝力一杯、功徳(善)を修めよ〟とすすめるから、「修諸功徳の願」といわれている。
本願寺、本願を知らず、では済まされない。
これでも〝修善をすすめた文証など、あろうはずがない〟と言うのだろうか。
〝修善は獲信の因縁(宿善)になる〟というのは、間違いか。