

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
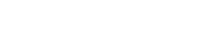
中外日報(平成20年2月26日)
宗門財施
保険活用で新財源を
まず論戦の口火を切った武田議員は、門徒の間でも寺院離れや宗門離れが進む危機的状況下でいかに宗門体力を維持するかについて、総局の見解を求めた。
「葬式仏教といわれて久しいが、今、その葬式や法事からも寺院や僧侶は必要とされなくなってきている」
「門徒であれば会費や寄付を要求される。門徒でなくても聴聞はできるし、寺に依頼しなくても葬儀社に相談すれば僧侶のあっせん、僧侶抜きの葬儀や法事をしてくれる。門徒であるメリットは、と問われたら何と答えればいいのか」
武田議員は、このような宗門や寺院を取り巻く厳しい現実に触れ「寺檀制度の名残や親類縁者のしばりの中で門徒意識が維持されてきた良き時代のぬるま湯に浸かってきた報いが、これから押し寄せてくるに違いない」と指摘。
このような危機的状況を間近に控え、(中略)このほど宗派が導入を決めた「あんのん医療保険」の加入奨励などで、新たな財源の確保に努めるべきだと求めた。
門徒離れが急速に進み財政が逼迫している本願寺が、財源確保のために医療保険を始め、門徒に加入を推進しています。
親鸞聖人の教えを布教するという、本来の目的から大きく逸脱し、門徒にすっかり愛想をつかされた挙げ句の果てに、とうとう保険業に手を染めた本願寺。
いったい、どこへ行こうとしているのでしょうか。
自滅に向かって加速しているのでは、と末路を嘆くのは、親鸞学徒だけではないようです。心ある住職は、自派本山の体たらくに、憤りをぶつけています。
中外日報(平成20年3月8日)
雑記
真宗 資料の適性配布を
「届出門徒戸数の二倍も送ってこられても…」。昨秋に創刊された親鸞聖人750回大遠忌の広報誌『安穏─京都からのメッセージ─』に対し、このような複雑な思いを抱いた住職も少なくなかったようだ。中には「あんのん医療保険」の全面広告が掲載されていたことについて「これを門徒らに配って、われわれ住職に保険の営業マンになれというのか」と強い不満を持った住職もいた。
それにしても、なぜ、こんな惨状に堕してしまったのでしょうか。
元はと言えば、門主をはじめ、伝道院も勧学寮も、全国末寺住職に至るまで、伝統にあぐらをかき、親鸞聖人の教えを現代人に伝える努力を疎かにしてきた、怠慢が招いた結果にちがいありません。
「いずれ、大変なツケに、苦慮されるのは、確定的である」(本願寺なぜ答えぬ)
の警告通りではありませんか。
真実開顕にばく進する親鸞会に、つまらぬ嫌がらせなどしている場合ではないでしょう。
自壊を食い止めるには、早く意地や我慢をかなぐりすてて、なぜ親鸞会に老若男女が、群参するのか、研究し、真似でもいいから光に向かって舵を斬る。
それしかないと、目覚めてもよさそうなのに、闇に向かってひた走る本願寺の鈍感さ、頑固さが、なんとも歯がゆいばかりです。