

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
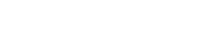
中外日報(平成20年7月12日)
「現代布教の閉塞感どう打開」
本願寺派教学伝道研がシンポ
───「節談」の可能性と限界探る───
講義形式が主流の現代の布教が閉塞感に陥っているとされる現状で、節談の可能性と限界を検証した」
と、本願寺聞法会館で行われたシンポジウムを記事は紹介しています。
「節談とは、美しい七五調の言葉に節(抑揚)をつけ、鍛え上げた美声と身ぶり手ぶりをもって演技的表現をしながら聴聞者の感覚に訴える情念の布教」
で、講義形式の布教が
「理が勝ちすぎて法義、安心を充分に伝えられていない」
とされる中で、節談が再び脚光を浴びつつある、という。
「伝道院で養成される今の布教使は同じタイプばかりで、現代の布教は〝壁〟に直面している」
という意見には、聴衆の武蔵野大学の山崎龍明教授が、
「現代の布教が〝壁〟に直面しているのは分かるが、だからと言ってなぜ節談なのか」
「問題なのは説教者と聴聞者のずれではないか」
と問題提起。最後はその「節談」の実演が行われたといいます。
説法は、「節談」か、「講義形式」か。
確かにそれも大事でしょう。
親鸞聖人の教えを、より多くの人に伝えるために、もっとも相応しい方法を模索すべきであることは言うまでもありません。
しかしその前に、まず知らねばならないのは、「親鸞聖人の正しい教え」そのものではないでしょうか。
親鸞聖人の教えを正しく知らずして、いくら説教しても、その形式が「節談」であろうが「講義」であろうが、聴衆に聖人の教えを誤解させる。それなら何も話をしないほうがよいのです。
では果たして現場の布教で、
「平生業成」(生きているときに救われる)
の親鸞聖人の教えが説かれているでしょうか。
「信心為本」(信心一つで救われる教え)
の浄土真宗が宣伝されているでしょうか。
「誠なるかなや、摂取不捨の真言、超世希有の正法」(まことだった、本当だった、弥陀の本願、ウソではなかった!)と、弥陀に救われたらハッキリすると、ハッキリ教えられているでしょうか。
この親鸞聖人の教えに反して、
「お念仏さえ称えて感謝の日暮らししていれば、死んだら極楽、死んだら仏」、
「いつとはなしに有り難くなったのが信心だ」
などという不浄説法がまかり通っているとすれば、それは形式云々以前の問題です。
こんな話は、浄土真宗ではありませんし、親鸞聖人の教えではないのです。
あるいは、自分の下らぬ信仰体験や新聞の切り抜き話、倫理道徳に毛が生えた程度の教訓話なら、どこにでも転がっている。
そんな話を、聞法者は聞きに来られたのではないでしょう。
親鸞聖人の本当の教えを聞きたくて、参詣されたのではないのですか?
またそうでなければ、そんな人は浄土真宗の「聞法者」でも「求道者」でもないので、落語や漫才でも聞きに行けばよいので論外ですが、その点を山崎教授も、
「問題なのは説教者と聴聞者のずれではないか」
と憂いておられるのではないでしょうか。
説法する者は、自身がまず親鸞聖人の教えを、正しく深く学び、体得する。その知らされた親鸞聖人の教えを、自分の考えを入れずに、お伝えする。これが「自信教人信」です。
「平生業成」「信心為本」の親鸞聖人の教えを、正しく知らずして、いくら説法の形式云々をあれこれ論じても、水面に描いた絵に終わるだけです。
論ずべき問題の本質を、見失ってはならないでしょう。