

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
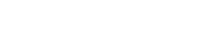
「おくりびと」に宗教が出てこない
中外日報(平成21年3月5日)「おくりびと」
真言宗の管長・松長有慶氏が、映画「おくりびと」を見ての所感を、次のように述べられています。
死の問題を考えさせられ、死を見送る姿が世界の人々の胸を打ったのだろうが、心配なことがあった。
それは死を正面からとらえ、評判になった映画でありながら、宗教が出てこなかったことだ。
これまで葬儀は僧侶の〝専売特許〟だったが、徐々にこのような雰囲気が広まれば、僧侶にとって大きな打撃につながるだろう。
「死」は、これから大きな課題になる。葬儀をせずにお別れの会をするという風潮が増える中、われわれは従来のやり方に安穏としてよいのか。
寺離れが進む昨今では、身内が亡くなっても「葬儀」をしない人が増えているようです。
「葬儀」はしても、すべて「葬儀屋」にまかせてセレモニーホールで行い、「読経」も通信講座で資格をとった"僧侶"付きなので、寺が関与する余地はなくなっています。
 こうして、重要な収入源である「葬儀」が減る一方であることが、寺院僧侶にとって「大きな打撃」であると、松長氏は「心配」されているのです。
こうして、重要な収入源である「葬儀」が減る一方であることが、寺院僧侶にとって「大きな打撃」であると、松長氏は「心配」されているのです。
このことをまた、「『死』は、これから大きな課題になる」とも憂えておられるのですが、果たして「死」はそういう意味で「大きな課題」なのでしょうか。
今までは課題でなかった「死」が、「葬儀」が減ってきてはじめて「これから」大きな問題になってくる、ということなのでしょうか。
寺院の経済的事情から言えばそうかも知れませんが、本来、仏教で「死」が問題にされるのは、どうしてなのでしょう。
これについて、松長氏は先に続けて、
お大師様(弘法)の教えでは「死」をどうとらえるのか。変化の時代の中で考えさせられることは多い。
と述べておられます。
仏教は、すべての人の死後(後生)に一大事がある、と説きます。
この生死の一大事、後生の一大事の解決こそが仏教の目的であると、釈迦は教えられているのです。
ですから親鸞会は一貫して、この問題の大切さを訴え続けてきました。
「死」は、「葬儀」が減りつつある「これから」始めて「大きな課題」になるのではなく、今までも、今も、今からも、いつの時代でも、常に「一大事」であり続けてきたのです。
「時代の変化」によって変わるものではありません。
親鸞聖人が、この釈迦の教えの通り、弥陀の本願力によって平生に「生死の一大事」を解決され、
"いつ死んでも浄土往き間違いなし"の大安心の身に救い摂られたのは29歳の時でした。
果てしない過去から迷い続けてきた「迷いの命」が死んだ時ですから、「心の臨終」であり「魂の葬式」です。
同時に、「人間に生まれたのはこれ一つであった」と生命の大歓喜が生まれた時です。
(詳しくは「死んだら賀茂川の魚に食わせよとなぜいわれたのか」)
この「魂の解決」を果たされた聖人は、
「親鸞閉眼せば、賀茂河に入れて魚に与うべし」(改邪鈔)
"親鸞死ねば、遺体を河に捨てて魚に食べさせてやってくれ"と宣言され、「盛大な葬儀も、立派な墓も要らぬ」と仰っているのです。
「肉体の葬式」には一切用事が無くなった聖人の、透徹した態度に驚かずにおれません。
この平生一念の弥陀の救いを明らかにすることが、釈迦一代の仏教の目的であることを、生涯、開顕していかれた方が親鸞聖人であり、その教えを「浄土真宗」と言われます。
親鸞会は、この浄土真宗・親鸞聖人の教えを明らかにしています。
「葬儀」とは、亡くなった方をご縁として、その本当の仏教を、僧侶は現代人に分かるように伝え、檀家門徒は聞かせて頂く。
これが本来の「葬式」や「法事」の意義なのです。
(「浄土真宗親鸞会」では、この意義に順っての葬儀を執り行ってもらえるので、参列者からは多くの喜びの声を聞きます)
本願寺のつとめる葬儀は果たしてどうでしょうか。
肉体の葬式ばかりに力を入れ、肝心の魂の解決、信心決定はまったく説かれていないのではないでしょうか。
葬式仏教と揶揄されながら、いよいよその葬式さえも僧侶は必要な時代となりつつあります。
本当の仏教とは何か。
生きている人に本当に「心配」すべきことは、どんなことか。
僧侶は何をなすべきか。
よくよく考えさせられる記事でした。