

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
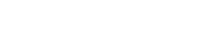
「易往而無人」の解釈を検証する
続いて、大谷氏の「易往而無人」の解釈を、検証しましょう。
これは「往き易くして人なし」という、『大無量寿経』に説かれているお釈迦様のお言葉です。
がんで最後が迫っているような厳しい体験がなくても、阿弥陀如来に救われていく道を明らかにしなければならないし、戦争という悲惨な状況でなくても、救われるべきものがあるのをあきらかにしなければならないというのが、仏教者としての私の基本的な姿勢です。
本当に深刻な病気の人には、救われたい、すがりたいという気持ちが準備されているから、「心配ないですよ、阿弥陀如来におまかせしなさい」と言うだけで通じます。
しかし、そうでない者にはそうはいきません。凡夫とは、楽をしたい生き物です。考えないですむ間は考えずに行こうとするものです。だからお浄土には「往き易くして人なし」(『仏説無量寿経』)ということになるのでしょう。
「後生の一大事」の説明と同様、「なにがなんやら、サッパリ分からない」というのが、私の率直な感想です。
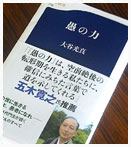 こう言っては失礼かも知れませんが、読んでいてこれ程イライラする文章には、めったにお目にかかれるものではありません。
こう言っては失礼かも知れませんが、読んでいてこれ程イライラする文章には、めったにお目にかかれるものではありません。
著者の「ごまかそう、ごまかそう」という腹が透けて見えるからでしょうか。
「いかに曖昧に書くか」の魂胆は、親鸞聖人が常に断言で説かれた布教精神とは、余りにも対照的ではありませんか。
「これが、聖人を祖と仰ぐ本願寺のトップなのか」と情けなく、哀れですらあります。
"なにもそこまで言わなくても"と、眉をひそめる人もあるかも知れませんが、よく考えてもみて下さい。私たちのもっとも知りたいことは、
「どんな人が浄土へ往けて、どんな人が往けない」のか、
「浄土へ往くには、どうすればよいのか」、
それを「親鸞聖人はどう教えておられるのか」、
でしょう。
その一番知りたいことが、どれだけ読んでもまったく分からないのです。
これでは、「本願寺の門主」として文章を書く意味がないじゃありませんか。
しかも「この部分だけでは分からない」のではありません。
『愚の力』全編くまなく探しても、
「浄土往生が決まる前と、往生が決まった後とでは、何がどう変わるのか。どうすれば浄土往生できる身になれるのか、親鸞聖人はどう教えておられるのか」
が、どこにも明示されていないのです。(「ここにある」と思われるところが見つかった人は、ぜひ教えてください)
こんなことで、よく「親鸞聖人の教えのすべて」などと言えたものだと、その蛮勇には感心させられます。
では、お釈迦さまが「往き易くして人なし(易往而無人)」と説かれているのは、どんなことなのか。
親鸞聖人も蓮如上人も、明らかに教えられているのです。
親鸞学徒の私たちは、その親鸞聖人、蓮如上人のご教導を仰ぎましょう。
「往き易くして人なし(易往而無人)」
とは、
「弥陀の浄土へは往き易いけれども、往っている人が少ない」
という意味です。
これはちょっと聞くと、論理的に合わないように思われるでしょう。
浄土が「往き易い」のならば「人が多い」はずだし、「少ない」とすれば、「往き易い」とはいえないからです。
では、釈尊の金言は何を意味するのでしょうか。
「浄土へ往き易い」と言われるのは、「大悲の願船に乗った人」のことです。
ここで「大悲の願船」とは、大慈悲の阿弥陀仏の本願を船に例えられた、親鸞聖人のお言葉です。
私たちの人生は、苦しみ悩みの絶えない海のようなものだと、聖人は「難度海」(苦しみの海)と言われ、その難度海の人生を明るく楽しく渡す大きな船が「弥陀の本願」なのだよと、『教行信証』の冒頭に、
「難思の弘誓は、難度海を度する大船」(教行信証総序)
と宣言されています。
この大船に乗せて頂き、「人間に生まれてよかった」と生命の大歓喜を得ることこそが人生の目的であると親鸞聖人は仰っています。
その弥陀の本願の大船に、聖人ご自身が乗せられた法悦を、こう告白されています。
「大悲の願船に乗じて、光明の広海に浮びぬれば、至徳の風しずかに、衆禍の波転ず」(教行信証行巻)
阿弥陀如来の本願に救い摂られたことを、「大悲の願船に乗じて」と言われ、「光明の広海に浮びぬれば」とは、暗く苦しい人生が、光明輝く人生に転じたこと。
「沈んで」いた人にのみ、「浮かんだ」という歓喜があります。
初めから「浮かんでいる人」はありません。
聖人が「大船に乗じて、浮かんだ」と言われているのは、「乗る前と、後とがある」ということであり、「乗る前は、沈んでいた」ということです。
 「至徳の風静に」とは、無上の功徳(南無阿弥陀仏)と一体となった幸せのこと、
「至徳の風静に」とは、無上の功徳(南無阿弥陀仏)と一体となった幸せのこと、
「衆禍の波転ず」とは、不幸や災難が、喜びに転じ変わることですから、全体の意訳はこうなります。
「大悲の願船に乗って見る人生の苦海は、千波万波きらめく明るい広海ではないか。順風に帆をあげる航海のように、なんと生きるとは素晴らしいことなのか」
まさしく聖人の、キラキラ輝く乗船記と言えるでしょう。
だから皆さんも早く、弥陀の大悲の願船に乗せて頂きなさいよ、と親鸞聖人は教え勧めておられるのです。
「大悲の願船に乗った」ならば、人生が浄土への楽しい航海になる。
歩行の旅は山あり谷ありで難渋しますが、船旅は船頭まかせで快適となります。
弥陀の本願の大船に乗れば、大悲の風にうちまかせて安楽に浄土に往けるから、これほど「往き易い」ことはないことを、
「易往(弥陀の浄土へは、往き易い)」
と言われているのです。
ではなぜ、「浄土に人が少ない」と言われるのでしょうか。
親鸞聖人の説明は、こうです。
「易往而無人」というは、「易往」はゆきやすしとなり。本願力に乗ずれば、本願の実報土に生るること、疑いなければ往き易きなり。「無人」というは、ひとなしという。人なしというは、真実信心の人は、ありがたきゆえに、実報土に生るる人稀なりとなり(『尊号真像銘文』)
「弥陀の浄土へは『往き易い』と、釈尊が言われているのは、大悲の願船に乗った人のことである。
弥陀のひとり働きで往く世界だから、『易い』という言葉もいらぬ易さだ。『人なし』と言われるのは、大悲の願船に乗る人が稀だからである」
蓮如上人の解説も同じです。聞いてみましょう。
これによりて『大経』には「易往而無人」とこれを説かれたり。この文の意は「安心を取りて弥陀を一向にたのめば、浄土へは参り易けれども、信心をとる人稀なれば、浄土へは往き易くして人なし」と言えるは、この経文の意なり(『御文章』)
「安心をとる」も「信心をとる」も、"弥陀に救い摂られて、大悲の願船に乗ったこと"ですから、意味はこうなります。
「弥陀に救い摂られ、大悲の願船に乗った人は、浄土へは『往き易い』けれども、大悲の願船に乗る人が少ないので釈尊は、『往き易くして、人なし』と言われているのである」
このように、釈尊の「易往而無人」と言われた真意を、親鸞・蓮如両上人がねんごろに解説されている御心は、
「誰でも彼でもみんな『死んだら極楽、死んだら仏』ではないのだよ。『浄土へ往生している人は少ない』とお釈迦さまは仰せではないか。だから一日も片時も急いで『往生一定』の身に救われなさいよ。早く一切が往生の碍りとならない『無碍の一道』に出てもらいたい。それには火の中かき分けてでも仏法を聞きなさいよ」
という、「平生業成」の教え以外にないことも、鮮明に知られされるではありませんか。
 ところが大谷氏の解説では、親鸞聖人も蓮如上人も、私たちに何を勧めておられるのか、なにをどうすればいいのか、さっぱり分かりません。
ところが大谷氏の解説では、親鸞聖人も蓮如上人も、私たちに何を勧めておられるのか、なにをどうすればいいのか、さっぱり分かりません。
本願寺の教えは、浄土真宗の教えとは似て非なる、というよりも「似ても似つかぬ」別物なのです。
おそらく、前著『朝には紅顔ありて』の時に、親鸞会から、「親鸞聖人のお言葉を提示していないじゃないか」と批判されたのが身に応えたのでしょう。
それで今回の『愚の力』では、少しでも仏教の言葉を出そうとつとめたにちがいありません。
その反省と向上は一応は評価できます。
だが、どれだけ仏語を出してカムフラージュしようとも、中身が浄土真宗とは根本的に違っているのですから、偽装のしようがありません。
むしろ繕えば繕うほど、馬脚をあらわし破滅に向かう悪循環に陥っているのが、本願寺の、哀れにも悲しい現実といえるでしょう。
いずれにせよ、親鸞聖人の教えとは正反対のベクトルにバク進していることだけは、間違いありません。
『愚の骨頂』と揶揄される程度では済まなくなる前に、早く気がついて頂きたいものです。