

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
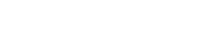
北陸中日新聞(平成21年4月14日)
少子高齢化で檀家に重い負担
「寺の施設改修などの普請は、檀家が寄付で支えてきた。だが少子高齢化で、檀家数は減る一方だ。普請費用工面に苦悩するケースも多い。費用負担は、どうすればいいのか」
と、寺の運営にとっての深刻な問題を記事は提起し、檀家の苦悩を紹介する。
《寺の普請費 悩む寄付頼み》
「昨年12月、寺の修復工事への寄付を要請する手紙が届いたが、年金生活で、そんな余裕はない」
静岡県内の檀家で、首都圏在住の60代の男性が悩みをこう打ち明けた。手紙では本堂、庫裡、山門の屋根などの修理費が約1億3000万円と見積もられ、一軒当たり30万円以上を、2011年3月末までに寄付することを要請していた。
割り当てた額を、まるで税金のように檀家からむしり取るシステムに、仏法者として強烈な違和感、嫌悪感を禁じ得ない。
そもそもが、「何のために寺は必要なのか」を、住職も檀家も考えられたことはあるのだろうか。
議論の出発点は、まずそこであろう。
墓を守るため?
葬式や法事を行い死者を供養するため?
そうだ、と言われるならば、いずれも間違いである。
仏教には本来、墓を作る教えはない。
お釈迦様は、死者のために仏事を行われたことは、一度もない。
むしろ、それら世俗的、形式的な儀礼を避けて、生きている人に人生の目的を教示されたのが仏教なのである。
高森顕徹先生の『歎異抄をひらく』に見てみよう。
葬式や年忌法要などの儀式が、死人を幸せにするという考えは、世の常識になっているようだ。
印度でも、釈迦の弟子が、「死人のまわりで有り難い経文を唱えると、善い所へ生まれ変わるというのは本当でしょうか」と尋ねている。
黙って小石を拾い近くの池に投げられた釈迦は、沈んでいった石を指さし、「あの池のまわりを、石よ浮かびあがれ、浮かびあがれ、と唱えながら回れば、石が浮いてくると思うか」と反問されている。
石は自身の重さで沈んでいったのである。そんなことで石が浮かぶはずがなかろう。
人は自身の行為(業力)によって死後の報いが定まるのだから、他人がどんな経文を読もうとも死人の果報が変わるわけがない、と説かれている。
読経で死者が救われるという考えは、本来、仏教になかったのである。釈迦八十年の生涯、教えを説かれたのは生きた人間であり、常に苦悩の心田を耕す教法だった。死者の為の葬式や仏事を執行されたことは一度もなかったといわれる。
むしろ、そのような世俗的、形式的な儀礼を避けて、真の転迷開悟を教示されたのが仏教であった。
今日それが、仏教徒を自認している人でも、葬式や法事・読経などの儀式が、死人を幸せにすることだと当然視している。その迷信は金剛のごとしと言えよう。
そんな渦中、
「親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一返にても申したることいまだ候わず」
の告白は、まさに青天の霹靂であるにちがいない。
寺の修復費には、それ相応の額がかかるだろう。
だが、まず問題なのは、住職が本来の仏教精神に生き、寺がその機能を果たしているか、どうか、なのである。
もし寺が、「この世から未来永遠の幸福」に私を救う「仏教」を聞き、人にもお伝えする聞法道場になっているならば、どれだけ布施しても惜しくはない、という気持ちの人があって当然だろう。
浄土真宗親鸞会の親鸞学徒が、聞法ドメインなど種々のご縁に財施される心は、まさにそんな気持ちからなのである。
勿論、それぞれに経済事情があろうけれども、その中、「精一杯が尊い」と、いつも高森顕徹先生が教導され、講師が言われているのも、額の大小が問題なのではなく、布施をする心の向きこそが大切だからである。
「寺が、寄付金を、門徒や檀家に、強制的に割当てている」などという、この記事のようなことを聞いたり読んだりすると、常に仏法精神を教えて頂いている親鸞会会員は、びっくりする。
「割り当て」など、親鸞学徒からは出てこない発想だからである。