

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
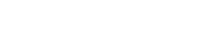
本願寺新報(機関新聞)の「丸ごと解説・日常勤行聖典」と題するコーナーで、「阿弥陀仏と釈尊」について述べられていました。文責は、教学伝道研究センターの佐々木義英氏となっています。
「真実の教えは誰から聞く?」という見出しで、こう書かれていました。
「浄土真宗」の「真(真実)」の意味についてうかがってきましたので、続いて「宗(教え)」の意味について考えてみましょう。
これまで皆さんと学んできたことから、「浄土真宗」という言葉の意味をまとめてみますと、「阿弥陀仏の浄土に往生する真実の教え」ということになります。
ところで、私たちは、この「教え」を「誰から聞いて」知っているのでしょう。もちろん、私たちに「浄土真宗」のこころを広くあきらかに示してくださったのは、親鸞聖人です。それでは、親鸞聖人は、誰からお聞きになったのでしょう。
(中略)
つきつめて考えていきますと、「阿弥陀仏の浄土に往生する真実の教え」は、釈尊から聞いているということになるでしょう。
(中略)
それでは、お二方の関係は、どうなっているのでしょう。
(中略)
釈尊は、その(阿弥陀仏の)願いに応じるかたちで、私たちに阿弥陀仏のおこころを伝えてくださっている、ということなのです。
このように「阿弥陀仏と釈尊とは、違う仏さまである」と、きちんと分けて書かれている文章を、本願寺の出版物の中では初めて見たので、とても意外な印象を受けました。
「いや、そんなことはない、本願寺でも常に説いている。それをあなたは知らないだけだ」
と、反論される人はあるでしょうか。
富山県のある末寺の門徒総代を何十年と務めてきた人が、チラシを見て親鸞会の講演会に参詣されて初めて、
「阿弥陀仏とお釈迦さまが違う仏さまだということを、初めて知りました。今まで、こんなこと聞いたことありませんでした。それどころか、神と仏の違いも教えてくれませんでした。本願寺にダマされ続けてきました」
と、怒りと無念の思いを露にされるのを見るにつけ、
「本願寺では、阿弥陀仏と釈尊との関係は、まったく説かれていないのだなあ」
と嘆息せずにおれませんでした。これが本願寺の実態でしょう。それとも、この元・門徒総代(今は親鸞学徒となっておられます)の方だけが、全国2万の本願寺末寺の中で特殊な例なのでしょうか。そうであれば、それに越したことはありません。
いずれにしましても、「阿弥陀仏と釈尊」との違いは、大いに説かねばならないことです。というよりも、この違いが分からなければ、親鸞聖人の教え・浄土真宗は絶対に分からないのですから、「浄土真宗・本願寺」と看板を掲げる限りは、御門徒の皆さんに徹底しなければならないことなのです。
その点、機関紙にようやく、「阿弥陀仏と釈尊」とは違う仏さまであることを述べたことは、一応は評価できるでしょう。
しかし、この後の結論が、頂けません。
私たちは、釈尊の説法によって、はるか2500年の時を超えて、阿弥陀仏の願いを聞き、そして、親鸞聖人のお導きによって、阿弥陀仏のはたらきのうちに救い取られているという「教え」にであっているということなのです。
やはり「十劫安心」の異安心です。「異安心」とは、親鸞聖人・覚如上人・蓮如上人のお三方の信心と、異なる信心のことです。本願寺の誤りは相変わらず根深いことが知らされるではありませんか。検証してゆきましょう。
「阿弥陀仏のはたらきのうちに救い取られている」という「教え」とは、一体どういうことでしょうか。普通に読めば、
「生まれたときから、すでに阿弥陀仏に救われている」
と誰もが理解するでしょう。これが「阿弥陀仏の浄土に往生する真実の教え」なのだと言っているのですから、本願寺では、
「生まれたときからすでに救われていて、死ねば誰でも浄土に往生できる」
これが「本願寺の教え」であることは明白です。
しかし、こんなことは、親鸞聖人も覚如上人も蓮如上人も、どこにも教えておられません。これを「十劫安心」の異安心と言い、浄土真宗では間違った信心として排斥されています。
折角、機関新聞で「阿弥陀仏と釈尊は、違う仏さま」であることは言っていても、上記のように根本的に「死んだらお助け」の異安心ですから、正しく教えが伝えられていないのです。
その一端を言えば、釈尊の一切経の結論である、
「一向専念無量寿仏」
がどこにも明示されていない、ということです。
「無量寿仏」とは阿弥陀仏のことですから、これは、
「阿弥陀仏一仏に向け、阿弥陀仏だけを信じよ」
ということであり、蓮如上人はこれを、
「一心一向というは、阿弥陀仏に於て二仏を並べざる意なり」(御文章)
「釈迦が『一向専念・阿弥陀仏』と説かれているのは、阿弥陀仏と他の仏を並べてふらふらしないことである」
と分かりやすく教導されています。「阿弥陀仏以外の仏や菩薩や神には向くな、心をかけるな、捨てよ」ということです。この釈尊の教えを親鸞聖人は、
「一向専念の義は、往生の肝腑、自宗の骨目なり」(御伝鈔)
「往生の一大事は、弥陀一仏を一向専念するか、否かで決まるのだ。ゆえに浄土真宗では『一向専念 無量寿仏』より大事な教えはないのである」
とまで言い切られています。
では、なぜ釈迦は、「阿弥陀仏一仏に向け。他へは向くな、心をかけるな」と厳しいのでしょうか。それは、「阿弥陀仏の他に、私の後生の一大事を助けてくださる仏はましまさないから」なのだと、釈迦が仰っていることを蓮如上人は、そのままこう記されています。
「夫れ、十悪・五逆の罪人も、(乃至)、空しく皆十方・三世の諸仏の悲願に洩れて、捨て果てられたる我等如きの凡夫なり。
然れば、爰に弥陀如来と申すは、三世十方の諸仏の本師・本仏なれば、(乃至)、弥陀にかぎりて、「われひとり助けん」という超世の大願を発して、われら一切衆生を平等に救わんと誓いたまいて、無上の誓願を発して、已に阿弥陀仏と成りましましけり。この如来を一筋にたのみたてまつらずば、末代の凡夫、極楽に往生する道、二も三も、有るべからざるものなり」(御文章)
「十方世界の仏方から『救い難き者』と見捨てられたのが我々である。そんな者を阿弥陀如来という諸仏の本師本仏が、ただお一人『私が助けよう』と立ち上がられ、崇高な超世の誓いをかかげて、実現できる準備を完了されているのだ。だから阿弥陀仏の救いによらなければ、我々の極楽に往生する道は二つとないのである」
親鸞聖人も蓮如上人も、この「一向専念阿弥陀仏」の釈迦の教えを、生涯、徹底して叫ばれた方でした。そのために親鸞聖人は、神信心の権力者の反感を買い越後流刑のご苦労をなされたのです。蓮如上人も賞金首をかけられ常に命を付け狙われたのでした。
「死んだら誰でも極楽に往ける」という本願寺の教えからは、この厳しい「一向専念阿弥陀仏」の教えが出てくるはずがないのです。本願寺では、「何を信じていても、何に手を合わせていても、誰でも死にさえすれば、極楽へ往ける」というのですから。
この「後生の一大事」が抜けているから、万事ことなかれ主義で、他宗に気を遣って「一向専念」を説かない。説けるはずもない。それどころか、「宗派を超えて手を取り合って」などと聖人の御心を踏みにじる暴挙に出て平気なのです。 さらには「大谷光真門主がローマ法王に謁見」と、本願寺トップが外道(仏教以外の教え)に頭を下げて喜んでいる姿に至っては、末期症状を過ぎたと言わざるを得ません。
この現状を、親鸞聖人はどうご覧になっていられるでしょうか。
「かなしきかなやこのごろの
和国の道俗みなともに
仏教の威儀をもととして
天地の鬼神を尊敬す」(悲歎述懐和讃)
「なんと悲しいことか。現今の日本の僧侶も在家の者も、外見は仏教を信じているように装っているが、内心はみな鬼神に仕えている」
「外道梵士尼乾志に
こころはかわらぬものとして
如来の法衣をつねにきて
一切鬼神をあがむめり」(悲歎述懐和讃)
「手には数珠をかけ身には袈裟を着て、いかにも仏法者らしく振舞っているけれども、心は外道と少しも変わらず、みな鬼神を崇めている」
聖人のご悲嘆が聞こえるではありませんか。
一応は「阿弥陀仏と釈尊」と銘打って、「浄土真宗らしく見える」何かを書いてはいても、「阿弥陀仏のおこころ」も、「親鸞聖人の教え」も、まったく伝えられていない本願寺の悲しき実態が、ここにあるのです。
崩落へのカウントダウンを止める自浄作用は、果たして残っているのでしょうか。