

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
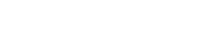
中外日報(平成20年10月18日)
《築地本願寺で記念法要厳修》
浄土真宗本願寺派の築地別院で、「寺基移転350年記念法要」が行われたという。
大谷光真門主は、念仏の生活の素晴らしさの根本である畢竟依、人生の最後のより所に言及し「お念仏をいただく私たちは心和らぎ、1人1人のいのちが輝く世の中を目指し僧侶、聞信徒が共に手を携えお念仏の輪を広げていきましょう」と説いた。
いつものように「念仏の生活の素晴らしさ」「お念仏をいただく」「お念仏の輪を広げる」など、なんとなく分かるようで、実は何の事やらさっぱり分からない言葉のオンパレードです。
本気で意味を知ろうと思ったら、素朴な疑問が噴出してくるのではないでしょうか。
私は大いに起きます。挙げてみましょう。
「念仏の生活」とは、「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、とにかく念仏をたくさん称える生活」のことだろうか。
もしそうなら、その生活が「素晴らしい」とは、どんなことか。
よく浄土真宗の老齢な方が、「病気もせず、家族平和で暮らしてゆけるのも、みんな阿弥陀さまのおかげや。ああ有り難い、ナンマンダ、ナンマンダ」と喜んでいられるが、これが「念仏の生活」のことで、喜んでいるから「素晴らしい」ということなのか。
もうそうなら、病気や事故に遇ったらどうなるのだろうか。
家庭内に何かのキッカケでいざこざが起きたらどうなるのだろうか。
それでも、有り難いと喜べるのだろうか。
喜べなくなれば、「素晴らしい」とは言えないのではないか。
「念仏の生活」とは、そんなにもろいものなのか。
いつ崩れるか分からない「不安の生活」のことなのか。
「お念仏をいただく」とも言われているが、「お念仏をいただく」とは、何がどうなったことなのか。
一度でも念仏を称えたならば、その時に、「お念仏をいただいた」ことになるのだろうか。
そうなると、浄土真宗の人ならば誰でも最低1回は念仏を称えたことはあるだろうし、私も、家は禅宗だったが小学生の時、冗談の中で「なんまいだ~」と言ったことがある。
あるいは、墓の近くを通るときに、後ろから何かつけているような気がして、魔除けの気持ちで称えたこともある。
日本人ならこのように、何らかの形で一度は念仏を称えたことがあるだろう。
そうなれば、「念仏の輪を広げましょう」などと言われるまでもなく、日本人のほとんどが「お念仏をいただいた」人とは言えないだろうか。
しかし、そんな自覚をして生活をしている人は、いないだろう。
そうなると、「念仏をいただく」とか「念仏の生活」というのは、そんな自覚のないものなのだろうか。
ハッキリしないものなのか。
「お念仏をいただく前」と、「お念仏をいただいた後」とでは、どこが、どう変わるのか。それとも何も変わらないのか。
変わらないのなら、「お念仏をいただく」意味が無くなるし、そんな「お念仏の輪」を広げることも無意味になる。
そもそも、「お念仏の輪」とはどんなことか。
「念仏を称える人たちの集まり」のことなのか。
それを「広げる」とは、「皆さん、お念仏を称えましょう、できるだけ沢山、称えましょう」と呼びかけることなのか。
もしそうなら、「称えたらどうなるのですか」と私は聞きたいが、それにどう答えて頂けるのだろうか。
「極楽へ往けます」といえば「称名正因の異安心」で論外だから、そんなはずはない。
なら念仏称えても何も変わらないのだろうか。
変わらないのなら、そんな「念仏の輪を広げる」ことに、なんの意味があるのか。
考えれば考えるほど、ますます分からなくなるのです。
「それが計らいでダメなのですよ、何も考えるな」と、門主様や本願寺様はいつものように仰るかも知れないが、もしそうなら、「お念仏」についてあれこれ話すこと自体が計らいで、ダメなことになるのではないか。
そうなると、これら「念仏」についての光真門主の発言に意味があるためには、「念仏をいただく」こととはどんなことか、上に縷々述べたような事柄が、誰にでも分かるように明らかにされていなければならないのです。
しかし、その説明は、何処にもありません。
「この記事にない」というだけでなく、大谷門主の著書にも、他の法要の記録にも、何処にも見当たらないのです。
(ここにあるぞ、という方があれば、教えてください)
浄土真宗は、「信心」一つで救われる「唯信独達の法門」です。
「念仏」は報恩ですから、浄土真宗の教えを漢字8字で「信心正因称名報恩」といわれるのです。
その肝要の「信心」が明確にされていないから、「念仏の生活」といっても雲を掴むようで、「お念仏をいただく」といわれても曖昧模糊として、「お念仏の輪を広げましょう」の呼びかけも空しくこだまするだけなのではないでしょうか。
かかる悲しい実態の根本は、どこにあるのでしょう。説く立場の者が親鸞聖人のみ教えを知らずして、人に分かるように説けるはずもありません。
親鸞会では、つねに親鸞聖人が教えられた「信心」が、ハッキリと丁寧に説かれています。最も大切な「信心」を明らかにしてこそ、念仏の意味も明らかになります。
親鸞会と本願寺との、決定的な違いの一つです。
親鸞学徒の使命の重さを、痛感するばかりです。