

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
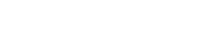
中外日報(平成21年2月10日)宗教不在、お別れ会
「葬儀めぐり熱い討議」
アカデミー賞を受賞した「おくりびと」の原作と言われるのが『納棺夫日記』。
その著者としている知られる青木新門氏を講師に招き、葬儀をテーマとするパネルディスカッションが、臨済宗本山妙心寺で行われました。
青木氏は、葬儀が宗教儀礼としての性格を弱め、故人とのお別れ儀式に変わりつつあると論じ、"死"が覆い隠されていることの弊害に強く警鐘を鳴らした、と記事にはあります。
討論では、
「葬儀に僧侶は不要ということになりかねない」
「臨終から納棺までが大切な時間なのだが、死者と語り合う場を社会が奪っている」
「葬儀の導師をしてもらった和尚が名刺も置かずに帰り、連絡先も分からない、といって突然納骨の相談に来た人もいる。和尚が、葬儀だけやって後は放っておくのでは、和尚なのか葬儀業者なのか分からない」
「お別れ会となってしまう葬儀の中に、宗教はどこにあるのか」
などの意見が交わされ、危機感を訴える住職もあったようです。
 さて、宗派によってそれぞれの葬儀の形はありましょうが、共通している問題の核心は、
さて、宗派によってそれぞれの葬儀の形はありましょうが、共通している問題の核心は、
「葬儀は誰のために、何のために行われるのか」。
この一点にこそ、あるのではないでしょうか。
何宗であれ、「仏教」を標榜する寺院である以上、仏教を説かれた釈迦の真意に添った葬儀でなければ、意味がありません。
ところが、上記のような議論を読む限り、危惧せずにおれないのは、まるで仏教が「納棺の儀式」であるかのように、住職でさえも誤解されていることです。
仏教で葬儀が開かれる意義は、参列した人が、亡くなった方をご縁として無常を見つめ、真実の仏教を聞き、本当の幸せに救い摂られることにのみ、あるのです。
もちろん葬儀が、故人との別れを惜しむ場であることは違いないでしょう。
法事で故人を懐かしまぬ人はないでしょう。
しかし、それだけで終わっては、別に僧侶に来てもらわなくてもよいことになります。
「家族だけですればよい」「葬儀屋に任せればよい」となるのも、当然です。
事実、「葬式仏教」「法事仏教」も今や衰退し消えようとしているのは、門徒や檀家が、それら形ばかりの因習に、相当のお金と時間と手間をかける意味をまったく見いだせないからではないでしょうか。
伝統にあぐらをかき、自ら仏教を学ぶ努力をしないで、本来の意味から大きくかけ離れた葬儀や法事に収入を頼ってきたつけが廻ってきたことを、そろそろ自覚されるべきでしょう。
浄土真宗親鸞会は、釈迦、七高僧、親鸞聖人、覚如上人、蓮如上人を一貫する真実の仏教を、常に研鑽する者の集まりです。
親鸞会で行われる葬儀や法事で必ず説法がなされるのは、参列者が仏教を聞いて本当の幸せになることこそが、故人の最も喜ばれることであり、親鸞聖人の御心にかなう法要であるからです。
要を抜いていくら議論しても結論は出ず、対策は水面に描いた絵とならざるをえないでしょう。