

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
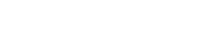
大谷光真氏(本願寺門主)と、上田紀行氏(文化人類学者)との対談本、「今、ここに生きる仏教」を読みました。これで分かったことは、
「ああ、やっぱり大谷門主は、阿弥陀仏も浄土も、信じておられないのだな。親鸞聖人の教えを、何にも知らない、だからあまり大切にも思っていない人だな」
ということです。
一貫してその発言には、阿弥陀仏の本願に遇わせて頂いた喜びも、親鸞聖人の教えをお伝えする使命感も、まったく感じられないのですから。
「現代人には、他力だとか阿弥陀仏とか言っても、どうせ無理だ。分からないのは仕方がない」
「親鸞聖人の教えを伝えるのは難しいからやめよう。そんなことより、ボランティア活動をすることで、教団の社会的面目を保つことの方が大事だ」
万事、こんな調子です。
ご本人は、浄土真宗、教団の危機的な未来を憂いて種々提言されているのですが、その原因が、自身の情けない信仰と、消極的な布教姿勢にあるとは、少しも気がついていないようです。それを、全国末寺の僧侶や幹部学者の責任のように思っているのですから、内部崩壊するのも道理でしょう。果ては、門徒の努力不足を愚痴るに至っては、もうつける薬がない、と言わざるを得ないでしょう。
結論である「あとがき」に門主は、こうこぼしています。
「今、多くの伝統仏教教団は深刻な困難に直面しています。もちろん、僧侶が自覚して努力すべきですが、一方で僧侶ではない在家の方々の影響力に期待したいと思います。現代は仏教に対する批判の言葉は充満していますが、厳しくても、頑張れと励まし育てるような言葉や行いが少ないように感じます。住職を育てるのは門徒や檀家、さらには縁のある人すべての責任という考えが社会に広がると、もう少しよい方向に進むであろうと思います」
(『今、ここに生きる仏教』より)
よくもヌケヌケと、こんな責任転嫁ができるものだと、その厚顔無恥ぶりには感心させらます。果たして、「本願寺の僧侶」を育てる責任は、誰にあるのでしょうか。もしそれが、「本願寺の門主にはない」とすれば、一体、「門主」とは、何をどうする立場なのでしょうか。単なるお飾りなのでしょうか。肩書きだけの名誉職でしょうか。
対談相手の上田氏は、「はじめに」にこう述べられます。
「本願寺派は寺院数一万を数える、日本仏教における最大宗派であり、その門主とは、宗祖親鸞聖人の血を引く、宗派のトップである。東京あたりに住んでいる人の感覚では分からないと思うが、真宗の中心地の北陸や中国地方、そしてかの京都では、ご門主はまさに御簾の向こうにおわします『天皇』扱いの方である」
(同)
なるほど、これではバカになるはずです。そういえば大谷門主は、『愚の力』という本も出されていますので、タイトル通りということでしょう。だいたい、弥陀も浄土も信じていない者が、世襲だからと「門主」に祭り上げられ、幼少からいつも天皇扱いで平伏されれば、人間、だれでも勘違いするのも無理ないでしょう。
こんなふうに書くと、「そこまで言わなくても」と思われる人もあるかも知れませんが、親鸞聖人の本当の教えを、常に高森顕徹先生から聞かせて頂いている親鸞学徒からいうと、親鸞聖人の生きざまと、門主の発言との、あまりに大きなギャップに、驚くばかりなのです。
顕著な例を挙げると、『恩徳讃』について上田氏から、
「ぜひ、『如来大悲の恩徳は身を粉にしても報ずべし』とは、いったいどういう意味なのかということを、ご門主様に伺いたいと思っていたんです。『報ずべし』というのは、何をやればいいんでしょう」
(同)
と尋ねられて、こんなことを言っています。
「さて、改まってご質問を受けたのは初めてなので、私も考えがまとまっていませんが、『御恩』というのは、阿弥陀様に救われて仏になるという救いをいただいているということですね。それに対して『報じる』といっても、阿弥陀様にまっすぐお返しすることはできないというか、返してもしようがない」
(同)
これが、親鸞聖人の御心を伝える教団の、トップの発言なのですから、ビックリするではありませんか。繰り返しますが、
「阿弥陀様に救われた御恩を、阿弥陀様に返してもしようがない」
紛れもなく、これが本願寺門主の信仰なのです。親鸞聖人の、
「如来大悲の恩徳は、身を粉にしても報ずべし」
の恩徳讃の、これが門主の解釈ですから、末寺僧侶の信仰・布教も推して知るべしでしょう。これだけではありません。さらに脱線します。
「ですからその方向を変えて、世の中に向かって自分のできることを精一杯する。第一義的には、阿弥陀様に救われたという浄土真宗を、今度は周りに伝えていくということだろうと思いますが、必ずしもそこにとどまらなくて、社会的な活動でも、自分がいいと思ったことをする。自分の利益のためにではない、取引としてやる仕事でもないところに働きかける。私が味わっているというか、受け取っているのは、そういうことです」
(同)
トップがこんなことだから、浄土真宗が滅びる。教団は壊滅する。当たり前です。
29歳の御時に、弥陀に救われられてから、90歳でお亡くなりになるまでの、親鸞聖人のご一生はどうであったか。
他力の信をえん人は
仏恩報ぜんためにとて
如来二種の廻向を
十方にひとしくひろむべし
と、阿弥陀仏の救いを、一人でも多くに伝えられることのみに、生涯を捧げられた方ではなかったのでしょうか。
31歳の肉食妻帯の断行は、出家も在家も男も女も等しく救いたもう『弥陀の本願』を明らかにされるために、「堕落坊主」「破戒坊主」「色坊主」の謗りを覚悟でなされた破天荒の言動でした。
34歳の三大諍論は、法然門下・380余人の法友の、『弥陀の本願』の聞き誤りを正された、大きな論争です。
35歳で越後流刑になられた承元の法難も、「弥陀一仏に向け、弥陀のみを信じよ」と強調されたのが、その真因であったのです。
40歳を過ぎられ関東で20年、伝えてゆかれたのも「往生極楽の道=弥陀の本願」以外になかったことは、『歎異抄』2章・冒頭のお言葉からも明らかでしょう。その関東で、豪雪の中、日野左衛門の門前で石を枕に雪を褥(しとね)に休まれたのも、山伏弁円の剣の下に出会われたのも、「なんとか阿弥陀仏の救いを伝えたい」の御心以外にありませんでした。そのご苦労も、門主ともあろう方ならご存知のはずでしょう。
60歳過ぎに京都へ戻られてからも、種々の問題が起きる中、ご布教とご執筆に励まれたこと、そして84歳の御時には、50歳の長子善鸞を義絶されねばならなかったことは、聖人のご一生の中でも最もお辛い事件であったにちがいありません。「仏法をねじ曲げた我が子のために、幾億兆の人々を地獄におとすことはできぬ」と、これもまた、断腸の思いでなされた、私たちのための忍従であったのです。
かくして、90歳まで「弥陀の本願を伝える」ことのみに徹し抜かれた聖人の、『恩徳讃』そのままの生きざまに親鸞学徒は、「今の私の仏縁は、親鸞さまが命がけのご苦労してくだされたなればこそ」と、感泣せずにおれないのです。
それでも、返しきれない御恩に泣かれた親鸞聖人は、御臨末に、
我が歳きわまりて、安養浄土に還帰すというとも、和歌の浦曲の片男浪の、寄せかけ寄せかけ帰らんに同じ。一人居て喜ばは二人と思うべし、二人居て喜ばは三人と思うべし、その一人は親鸞なり
(御臨末の書)
〝まもなく親鸞、今生の終わりがくるだろう。一度は弥陀の浄土へ帰るけれども、寄せては返す波のように、すぐさま戻って来るからな。一人いるときは二人、二人のときは三人と思って下され。嬉しいときも悲しいときも、決してあなたは、一人ではないのだよ。いつも側に親鸞がいるからね〟
無窮の波動のように、衆生救済に生き抜かれた聖人でしたが、なおも
〝小慈小悲もなき親鸞に、他人を救おうなど、おこがましい。まことの衆生済度は仏のさとりを開いてからだ〟
と、つくづく述懐される親鸞聖人。
その聖人の教えを伝えるべき「本願寺の門主」が、
「阿弥陀様に救われた御恩を、阿弥陀様に返してもしようがない」
と嘯いているのですから、あきれ返る他ないではありませんか。
門主はなおも、ノンキに続けます。
「何かを受け取ったらその人に返すという往復運動だと、横へも将来へも広がらないですよね。実際、阿弥陀様に向かって『ありがとうございました』と言うのは大事なことですし、それはおろそかにしてはいけないと思いますが、そのことは、『身を粉にしても報ずべし』だとは、私には感じられない」
(『今、ここに生きる仏教』より)
阿弥陀さまから何にも受け取っていないのだもの、「身を粉にしても報ずべし」の『恩徳讃』が出てくるはずもありません。
上田氏の『恩徳讃』の質問に、最後はこう締めくくります。
「三十年くらい前の話ですけど、真宗の若い人との集まりで、『恩徳讃はそんな声高に大きな声でうたえるような内容ではないじゃないか』と言った人がいるんです。すると別の人が、『できないから、せめて一生懸命うたって、自分に言い聞かせたほうがいいんじゃないか。うたわなかったら意識もしなくなる』という説を唱えたんです。それぞれ一面あるとは思ったんですけど、久しくそれについて考えてこなかったので、昔のことがよみがえってきた感じです」
(同)
もう充分でしょう。悲しきかな、これが本願寺トップ、大谷門主の仏法の理解であり、信仰なのです。弥陀からの頂きものがない人に、どうして「身を粉にしても」の報恩が出てくるでしょうか。正直と言えば正直ですが、あまりにも情けないではありませんか。
29歳で弥陀に救い摂られてより、
「極悪の親鸞を、絶対の幸福に救いたもうた弥陀如来の広大無辺なご恩徳には、身を粉にしても報いずにおれない。どうすれば、どう伝えれば」
と永久に悩み続けられる親鸞聖人と、
「『恩徳讃』について久しく考えてこなかった。『報ずべし』の意味を尋ねられて、昔のことがよみがえってきた感じ」
などと寝ぼけたことを平気で言う、しかも己の無信仰を棚に上げて、
「教団が危機なのは僧侶のせいだ、門徒が悪い」
と責任転嫁する門主。
生きる世界が全く別次元であることがお分かりでしょう。
出版業界で長年、次々と出される新刊の評価・選定に辣腕をふるったある人は、この大谷光真氏の対談本「今、ここに生きる仏教」を一読して、
「こんな恥ずかしいものを、よく出せましたね」
と評されていました。浄土真宗の専門家でなくても、そのお粗末ぶりは分かるものなのだな、「門主」という肩書きのメッキで繕ってみても、中身がカラッポだということは、分かる人には分かるものなのだな、とつくづく感心しました。それほど酷い内容だということです。深い反省を促したいと思います。