

それは聞いてはいけないんだ。
強制されたことはありません。
寺の法話ピンとこない事ばかり
善知識はおられない。
どんな人生設計も死で崩れる。
本当に感謝せずにおれません。
分かって貰えないと思いました
因果の道理を教えていただいて…
東大理科三類(医学部)合格。
幸せな時間を嬉しく思います。
東大大学院「全優」成績表公開
初めて親の恩が知らされた。
考え直すよう言われます。
何度参詣するかは個人の自由。
心配は杞憂に終わりました。
恩知らずが申し訳なく。
なんと父が祖母と親鸞会に参詣
おかげて真実聞くことできた。
大谷派の近代教学は全く誤り
御名号こそ真宗の正しい本尊
教えを聞きたくても。
空いた口が塞がりません。
本願寺の僧侶の説法に愕然
人生に後悔はないと確信
本願寺別院輪番が説法もなく。
廃れていたのは本願寺だった。
会場の部屋は満席、立ち見も。
『正信偈』の冒頭の意味
「死んだら極楽」と聞いてきた
親鸞会で初めて知りました。
これでは寺はどうなるのか
僧侶の決まり文言死んだら極楽
しばらくご縁のないまま…
親鸞会さんはちゃんとしとるね
本願寺門徒でスパイの気持ちで
親鸞会でお話を聞いて感動
役僧「分からんでも仕方ない」
寺の住職の意識改革が絶対必要
東本願寺は死後を否定しながら…
家庭法話を続けてよかった。
本願寺を見切りました
最初の五分仏教、後は喧嘩の話
住職の信じ難い言葉に唖然
「あて所に尋ねあたりません」
と郵便物が返っくるのです。実体のない団体なのでしょうか?
すごい形相で怒り出しました。少しこわかったです。
「仏教の目的はなんですか」
「それは分からん」
「では本願寺の目的は」
「それは親鸞会に指摘されているとおり、葬式、法事ばかりになってしまっているのが現状です」
実名でメールを送っても名乗らない
本願寺も親鸞会はカルトではない
高額な財施を募っている?
高森顕徹先生に無条件服従を強いられる?
家族関係がうまくいかなくなったのも、全部親鸞会のマインドコントロールによる?
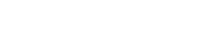
時代の流れ読もう───「寺離れ」は危機的
「今地方では、駅前商店街などの『シャッター街」化が問題となっています。
従来型の商店街が、郊外に新規出店してきた大型スーパーなどにお客を取られ、衰退しているのです。
そして日本の仏教界も、この様子に似ているのではと私は思っています」
仏教界の衰退を憂う、新潟県仏教会会長・加藤朝雄氏の寄稿です。
「今、寺院や僧侶は社会から見放されつつあるのではないでしょうか。私は危機感を感じています」
「新たに住職に任命される僧侶の最大関心事が『食べていける寺か』『出世できる寺か』というものになっていると聞きます。
寺院を盛り上げることより、初めから寺院にぶら下がろうとする気持ちの表れです。また寺院という財産や住職という肩書きにしがみつく僧侶も増えています。
行きもしない兼務住職地を離さず『小さな寺でも二つ三つ合わせればいい収入になる』と公言する人もいます」
と嘆かれ、
「今こそ僧侶は自己の意識を変えるべきです」
と訴えておられます。
加藤氏は曹洞宗の住職ですが、浄土真宗のみならず、どの宗派の僧侶も実態は同じのようです。
では、仏教界がこのような危機的状況に陥っている原因は、どこにあるのか。
加藤氏の見解はこうです。
 「死んだ人への読経も大切ですが、生きている人へのお経の意義を説くことが本来やるべきことではないでしょうか」
「死んだ人への読経も大切ですが、生きている人へのお経の意義を説くことが本来やるべきことではないでしょうか」
衰退の理由を、〝生きている人に、お経の意義を説いてこなかったことだ〟と述べられる後半部分には、まったく同感です。
生きている人に、「なんのために生きているのか」という人生の目的を明らかにされたのが、釈迦の一切経であり、その釈迦の教えを分かりやすく、現代の言葉で分かるように伝えるのが、本来、寺に住む僧侶の役目であるからです。
その使命を見失い、檀家や門徒を財産のように思って、葬式法事の収入にあぐらをかき、自分の生活のことだけに汲々としている僧侶の怠慢が生み出した結果だと、氏は指摘されているのでしょう。
本来の仏教と僧侶の任務を、お釈迦さまのエピソードと親鸞聖人のお言葉を通して、『歎異抄をひらく』(高森顕徹先生・著)には次のように書かれています。
【葬式・年忌法要は死者のためにならないって? それホント?】
(原文)
親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一返にても申したることいまだ候わず(『歎異抄』第五章)
〔意訳〕
親鸞は、亡き父母の追善供養のために、念仏一遍、いまだかつて称えたことがない。
葬式や年忌法要などの儀式が、死人を幸せにするという考えは、世の常識になっているようだ。
印度でも、釈迦の弟子が、「死人のまわりで有り難い経文を唱えると、善い所へ生まれ変わるというのは本当でしょうか」と尋ねている。
黙って小石を拾い近くの池に投げられた釈迦は、沈んでいった石を指さし、
「あの池のまわりを、石よ浮かびあがれ、浮かびあがれ、と唱えながら回れば、石が浮いてくると思うか」と反問されている。
石は自身の重さで沈んでいったのである。そんなことで石が浮かぶはずがなかろう。
人は自身の行為(業力)によって死後の報いが定まるのだから、他人がどんな経文を読もうとも死人の果報が変わるわけがない、と説かれている。
読経で死者が救われるという考えは、本来、仏教になかったのである。
釈迦八十年の生涯、教えを説かれたのは生きた人間であり、常に苦悩の心田を耕す教法だった。死者の為の葬式や仏事を執行されたことは一度もなかったといわれる。
むしろ、そのような世俗的、形式的な儀礼を避けて、真の転迷開悟を教示されたのが仏教であった。
今日それが、仏教徒を自認している人でも、葬式や法事・読経などの儀式が、死人を幸せにすることだと当然視している。
その迷信は金剛のごとしと言えよう。
そんな渦中、
「親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一返にても申したることいまだ候わず」
の告白は、まさに青天の霹靂であるにちがいない。
*転迷開悟 迷いから覚めて、さとりを開くこと。
この後に、「親鸞は父母の孝養のためとて……」の真意が明らかにされています。
これでお分かりのように、お釈迦さまが教えを説かれた相手は「生きた人間」のみであり、その教えを書き残されたものが「お経」ですから、「死んだ人の供養のための」という考えは、本来の仏教をご存知ないところから来る誤解であります。
蓮如上人も、如来聖人よりお預かりしたご門徒に仏教を説かぬ僧職の怠慢を、こう誡められています。
「皆人の地獄に堕ちて苦を受けんことをば何とも思わず、又浄土へ参りて無上の楽を受けんことをも分別せずして、徒に明し空しく月日を送りて、更にわが身の一心をも決定する分もしかじかともなく、また一巻の聖教を眼にあてて見ることもなく、一句の法門を言いて門徒を勧化する義もなし。
ただ朝夕は暇をねらいて、枕を友として眠り臥せらんこと、まことにもって浅ましき次第にあらずや。静かに思案を廻すべきものなり。
この故に、今日今時よりして、不法懈怠にあらん人々は、いよいよ信心を決定して、真実報土の往生を遂げんと思わん人こそ、まことにその身の徳ともなるべし。これまた自行化他の道理にかなえりと思うべきものなり」(御文章)
五百年前の蓮師のご悲嘆は、そのまま現代の仏教界・真宗界への厳しい叱咤と受けとめずにおれません。
生きた人に生きた仏法を、分かる言葉で分かるようにお伝えできるよう、一層の研究工夫をしていくのが、これからの仏法者でしょう。
浄土真宗親鸞会では、身近で具体的な話題から、現代の人が親鸞聖人の教えに親しまれ、理解されるようにと、いろいろな試みがなされています。
そのおかげで、仏とも法とも知らなかった私も、若くして仏法とご縁を結び、親鸞聖人の教えを聞かせて頂けていることを感謝せずにおれません。
親鸞会の目的は、親鸞聖人の教えを、正しく、速やかに、1人でも多くの人に伝えること以外にありませんし、あってはなりませんと、高森顕徹先生がいつも言われている通りであると、日々実感しています。