

─本願寺僧侶の非難に答える─
レッスン1.人間の論理について
レッスン2.マインドコントロール
レッスン3.思考停止
レッスン4.トルストイ
レッスン5.まだ分からないのか
レッスン6.夢さめる
レッスン7.五逆罪
レッスン8.謗法罪
レッスン9.聴聞姿勢
レッスン10.感謝の心
レッスン11.不幸な人
レッスン12.自明なこと
レッスン13.幸福な人
レッスン14.真実は一つ
レッスン15.反証可能な真理?
レッスン16.三世因果
レッスン17.破滅の道
レッスン18.ナワをうらむ泥棒
レッスン19.無限の向上
レッスン20.仏法の精粋
レッスン21.日々の精進
レッスン22.疑謗と仏縁
レッスン23.信ずる衆生と謗る衆生
追記1.本願寺と親鸞会
追記2.作家吉川英治さんの悲嘆
追記3.「反響集」を読んで
追記4.横超の直道
追記5.信心数え歌
追記6.真実
追記7.絶対教判
追記8.マインドコントロール論不毛
追記9.冷血
追記10.広い視野?
追記11.学生時代の仏縁
追記12.勝興寺の惨状
追記13.仏恩と師恩
追記14.因果の道理
追記15.マインドコントロール?
追記16.無責任
追記17.あえてよかった
追記18.沈黙
追記19.錯誤相関?
追記20.一向専念
追記21.この程度
追記22.思い込み
追記23.意味のある苦しみ
追記24.二河白道
追記25.生きる目的ハッキリすれば
追記26.急いで急がず急がず急ぐ
追記27.ご恩を有難く感謝する者
追記28.光に向かって
 「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
マインドコントロールとは何か、そして、親鸞聖人の教えはいかなるものか、他力の信心とは何なのか、詳しく解説しています。
オススメです!
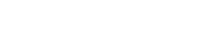
「浄土真宗本願寺派宗制」の改正案が、平成19年9月20日第284回臨時宗会で可決されました。
宗制とは、本願寺を支える〝もっとも根本的な最高法規〟とされるものです。
今まで間違っていた部分を正しく改めたから、「改正」なのですが、中でも注目されるのは「本尊」が改正されている点です。
今まで「阿弥陀如来一仏」としていたところが、「阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)一仏である」となったのです。
これは大変なことです。本尊という、仏教で最も大切な、根本に尊ぶべきものが変更されたのですから。
以下、具体的にどう変わったのか、述べてみましょう。
改正された最大のポイントは、「本尊」についてです。
※今まで↓
阿弥陀如来一仏である
※改正後↓
阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)一仏である
公式ホームページも同様に変更されています。(本願寺)
本尊については、真宗大谷派(東本願寺)も現在、「本派は阿弥陀如来一佛を本尊とする」としており、こちらはまだ改正の動きはありません。
本尊は根本に尊ぶべきもので、時代背景や場所、経済的な事情などによって変わってよいものではありません。
変わらないはずの本尊が改正されたということは、今までが根本的に間違っていたということを、自ら認めたと言うことです。
改正の理由について、本願寺新報には以下のように報道されています。
このたび「阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)一仏である」といたしましたことには、救済の法そのものである名号をともに示すことによって、尊号(※)を本尊とする形式を持つ浄土真宗の特色を表し、しかも最も一般的な六字名号をしめすことで、九字、十字名号等、尊号を代表させるという意図も含意するものであります。
(本願寺新報 平成19年10月1日号)
(※尊号-名号のこと)
本願寺が、本山を始め、別院、末寺にいたるまで、名号本尊ではなく、木像を本尊にしていたのは、本尊について規定した宗制のあいまいさによるものでしょう。
蓮如上人が
「他流には「名号よりは絵像・絵像よりは木像」というなり。
当流には「木像よりは絵像・絵像よりは名号」というなり。」
(御一代記聞書)
と、正しい御本尊を明確に教示されているにもかかわらず、これまでの「宗制」には、名号本尊についてはふれられていませんでした。
それが一転して、「名号本尊は、浄土真宗の特色」「救済の法そのものである名号」とまで言い切っています。
それでは今まで、なぜそうしていなかったのでしょうか。
それは、江戸時代、明治時代、戦前までは、本願寺という巨大教団は大きな権威であり、その寺の権威付けに、木像本尊が使われていたという経緯があるからです。
今でも本願寺の門徒の中には
「うちは、貧乏だから絵像だけど、寺には立派な金ぴかの木像がある」
という人があるほどです。
経済的に余裕のない人が絵像で、余裕のある人は木像だと思っている人が、今日でも多くあり、「名号より絵像が有り難い、絵像より木像がもっと有り難い」といった、まさに「他流」と蓮如上人が叱られた状態になっているのです。
江戸時代から、布教をしなくても門徒はどうせ離れないという前提で、本尊も、ただ寺の権威付けになるからという理由から、金ピカの木像にしたのでしょう。
大衆の迷った考えに迎合したもので、そこには、真実の教えがまったくありません。
親鸞会は、本尊について、一貫して、本願寺を追求してきました。
親鸞会発行の「親鸞会と本願寺の主張 どちらがウソか」は、初版が昭和51年です。
「どちらがウソか」とは、
親鸞聖人のご教示に反する本願寺の言動8項目を挙げ、その誤りを指摘し拡声を促すために広く公開してきました。(どちらがウソか 増補改訂版より)
という内容のものです。
その最初の項目をここに紹介しましょう。
(1)御本尊について
[親鸞会の指摘]
御本尊は「名号にせよ」と教示なされた親鸞聖人に背いて、本願寺は木像を本尊としているのは、重大な誤りである。
[本願寺の反論]
親鸞聖人も蓮如上人も、お名号をお書きになって本尊とせられました。
けれども絵像や木像をご安置していけないとか「本尊はお名号にせよ」とはおっしゃっていないのです。
事実、形像を礼拝の対象とされた例もあります。ご絵像・お木像にもそれぞれ意趣があるのです。
だから、本願寺では「本尊は必ずお名号でなければならぬ」と固執は致しません。
今日まで本願寺は、「名号本尊でなければならぬと固執は致しません」と言いながら、実態は、本山はじめ、全国の末寺はすべて木像本尊となっています。
木像本尊に固執し、名号本尊を無視しているのが現実の姿なのです。
親鸞会の「どちらがウソか」が発行されてから、30年以上が経過しても、本尊については、全く改める気配はありませんでした。
本願寺が、そのように木像本尊に固執している間にも、浄土真宗・親鸞会は、親鸞聖人、蓮如上人の教えられたとおり、ご名号本尊でなければならぬと訴え続けてきました。富山県の親鸞会館のお仏壇には、六字名号がご安置されています。
親鸞会の会員も、自宅のお仏壇は、みなさん御名号本尊を安置しています。
かつて本願寺で話を聞いていた人の中で、親鸞会とご縁があり、「正しい本尊は名号である」と親鸞聖人、蓮如上人が教えられていることを初めて知り、自宅の仏壇に、御名号本尊を安置するようになった人が非常に多くあります。
全国各地で名号本尊にされる人が増えるにつれ、親鸞聖人の教えと、本願寺の本尊が違うということがいよいよ明らかになってきました。そして門徒から末寺に、本願寺はなぜ木像本尊なのか、という不審や問い合わせが増えてきたのです。
それに加えて、時代はかわり、宗教離れ、地元を離れる人が多くなり、寺だから、伝統があるからと、布教をせず、葬式や法事、墓番をしているだけでは、門徒の数は激減。今や寺を支えている人の高齢化は進む一方で、戦後生まれの世代で寺を支えようという人は、ほとんどないのが現実です
本願寺新報にも、本願寺の現状に対する危機感がにじみ出ています。
さて、現代は、宗教を取り巻く社会の多様化や国際情勢の混迷などを背景として、宗教に対する懐疑、不安の増幅が叫ばれ、今や宗教界全体が社会的信用失墜の危機に瀕し、その存在意義を問われていることは、日本国内、そして本宗門においても例外ではありません。
宗教への無関心、無宗教化、宗教離れなど、将来の宗門存立に避けて通ることの出来ない問題が山積していることも紛れもない事実であります。(本願寺新報 平成19年10月1日号)
逆に、親鸞聖人の教えをそのまま伝える親鸞会館のご法話には、多くの若者が参詣しています。この結果の違いは、ひとえに最も大切な本尊から、親鸞聖人の教えられたとおりになっているかどうかの表れでしょう。
この現実を目の当たりにし、いよいよ本願寺も、今までのように門徒の皆さんを欺き通し、親鸞会の主張に対して強弁することが出来なくなりました。
さらに、「どちらがウソか 増補版」が親鸞会で発行され、今までの親鸞会と本願寺の本尊を巡っての論争の経緯が多くの人の目に触れることになりました。
教学上の根拠は本願成就文にあることも、明らかにされました。
浄土真宗の教義安心の至極である願成就文には、
「聞其名号 信心歓喜 乃至一念」
と教えられ、所信の体は名号であることが、明らかになっております。
もちろん、所信の体以外に御本尊はありえませんから、かかる本願成就文の教義安心から、親鸞聖人は名号ばかりを御本尊とせられたのであります。(どちらがウソか 増補版)
こうしていよいよ本当の親鸞聖人の教えと、それに反する本願寺の本尊の実態が明らかになってきたのです。本願寺が今回「名号は救済の法そのもの」「名号本尊は浄土真宗の特色」と言わざるを得なくなったのは、上記の理由があるからです。
できれば変えたくなかったというのが本音でしょうが、750回忌にむけ、宗制から変えざるを得なくなって、ようやくこのたび、
本宗門の本尊は、阿弥陀如来(南無阿弥陀仏)一仏である
と改正されたのです。
750回忌を前に、まず本山の本願寺から本尊を親鸞会のように御名号にすれば、右へならえで、次第に末寺も変わっていくことと思います。
「宗制」にしたがって、門主自らの手で本山の本尊を、名号本尊に変える日は近いでしょう。「宗制」は最高法規ですから、門主も当然、従わねばなりません。
もし、それが出来なければ、750回忌を待たずに「浄土真宗本願寺派」はこの世から消滅してしまうに違いありません。今が立ち直る最後のチャンスなのです。
口先だけの改正でないことを、切に念じております。