

─本願寺僧侶の非難に答える─
レッスン1.人間の論理について
レッスン2.マインドコントロール
レッスン3.思考停止
レッスン4.トルストイ
レッスン5.まだ分からないのか
レッスン6.夢さめる
レッスン7.五逆罪
レッスン8.謗法罪
レッスン9.聴聞姿勢
レッスン10.感謝の心
レッスン11.不幸な人
レッスン12.自明なこと
レッスン13.幸福な人
レッスン14.真実は一つ
レッスン15.反証可能な真理?
レッスン16.三世因果
レッスン17.破滅の道
レッスン18.ナワをうらむ泥棒
レッスン19.無限の向上
レッスン20.仏法の精粋
レッスン21.日々の精進
レッスン22.疑謗と仏縁
レッスン23.信ずる衆生と謗る衆生
追記1.本願寺と親鸞会
追記2.作家吉川英治さんの悲嘆
追記3.「反響集」を読んで
追記4.横超の直道
追記5.信心数え歌
追記6.真実
追記7.絶対教判
追記8.マインドコントロール論不毛
追記9.冷血
追記10.広い視野?
追記11.学生時代の仏縁
追記12.勝興寺の惨状
追記13.仏恩と師恩
追記14.因果の道理
追記15.マインドコントロール?
追記16.無責任
追記17.あえてよかった
追記18.沈黙
追記19.錯誤相関?
追記20.一向専念
追記21.この程度
追記22.思い込み
追記23.意味のある苦しみ
追記24.二河白道
追記25.生きる目的ハッキリすれば
追記26.急いで急がず急がず急ぐ
追記27.ご恩を有難く感謝する者
追記28.光に向かって
 「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
マインドコントロールとは何か、そして、親鸞聖人の教えはいかなるものか、他力の信心とは何なのか、詳しく解説しています。
オススメです!
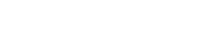
「余命一ヵ月の花嫁」という本が話題を呼んでいます。
「余命一ヵ月の花嫁」とは、乳がんと闘い、24歳で亡くなった長島千恵さんのこと。
TBS「イブニング・ファイブ」が報道し、全国に大反響の嵐を巻き起こした同名ドキュメンタリー番組を書籍化したものです。
イベントコンパニオンをしていた長島千恵さんは23歳の秋、左胸にしこりがあるのを発見、乳がんとの診断をうけた。
ちょうどそのころ赤須太郎さんから交際を申し込まれ、悩んだ末に「一緒にがんと闘おう」という言葉に動かされ、交際がスタートした。
だが、がんの進行は止まらず、去年7月に乳房切除の手術をせざるをえなくなる。
それでも治ると信じ、SEの資格を取り再就職、次第に病気のことは忘れていった。
ところが、今年3月、激しい咳と鋭い胸の痛みに襲われた。
胸膜、肺、骨にガンの転移が判明。
筆舌に尽くしがたい痛みと闘い、千恵さんは、この世を去られました。
「若いから、病気にならない、死なない、は間違い」
ということを同世代の人たちにも伝えたいと、ドキュメンタリー番組出演を決心したそうです。
そんな千恵さんのメッセージは心にひびきます。
「みなさんに明日が来ることは奇跡です。」
「生きてるのって奇跡だよね。
いろんな人に支えられて生きてるんだよね。
私これで元気になれたら、すごい人間になれると思う」
「こんな都会の空気でも、風って気持ちいいの。知ってる?」
ある日の二人の会話
「毎日、なにしてるの?」(太郎)
「生きている」(千恵)
生きているのは決して当たり前ではない。
しかし、人は誰も、生きていることを当たり前のように思っている。だから、苦しいことが起きると、こんなに苦しいのなら死んだ方がましだと、生きることを簡単に放棄する。
この体験記を読むと、生きることに、普段はいかにいい加減であるかを反省させられる人が多いでしょう。
千恵さんが生きられなかった今日を、この文章を読んでいる人は生きている。では、何のために生きているのでしょうか。
「私これで元気になれたら、すごい人間になれると思う」
という彼女の言葉にこめられた心を,すべての人は死を目前にして理解するでしょう。
人はただ生きているのではない。生きることには、重大な目的が有るのだと、親鸞聖人は教えられた。目前に死を迎えたとき、真に人生でなすべきことは何なのか、ハッキリと知らされるでしょう。
この生死の一大事を、平生の一念で解決できる無上の大法にあえた親鸞会の会員は本当に幸せな方です。
親鸞会発行の顕正新聞・論説にはこう書かれています。
問題は臨終の相ではなく、平生に後生の一大事が明らかに解決できているか、どうかである。
「平生の一念によりて往生の得否は定まれるものなり。平生のとき不定の念に住せばかなうべからず。平生のとき善知識の言葉の下に帰命の一念を発得せば、そのときをもって娑婆のおわり臨終とおもうべし」(執持鈔)
つまらん臨終の心配をせず、どんな臨終が来ても浄土往生間違いない身になるために、聴聞に身を沈め、信心獲得(心の臨終)こそ、急がなければならない。
(親鸞会発行・顕正新聞18年8月1日号論説より)