

─本願寺僧侶の非難に答える─
レッスン1.人間の論理について
レッスン2.マインドコントロール
レッスン3.思考停止
レッスン4.トルストイ
レッスン5.まだ分からないのか
レッスン6.夢さめる
レッスン7.五逆罪
レッスン8.謗法罪
レッスン9.聴聞姿勢
レッスン10.感謝の心
レッスン11.不幸な人
レッスン12.自明なこと
レッスン13.幸福な人
レッスン14.真実は一つ
レッスン15.反証可能な真理?
レッスン16.三世因果
レッスン17.破滅の道
レッスン18.ナワをうらむ泥棒
レッスン19.無限の向上
レッスン20.仏法の精粋
レッスン21.日々の精進
レッスン22.疑謗と仏縁
レッスン23.信ずる衆生と謗る衆生
追記1.本願寺と親鸞会
追記2.作家吉川英治さんの悲嘆
追記3.「反響集」を読んで
追記4.横超の直道
追記5.信心数え歌
追記6.真実
追記7.絶対教判
追記8.マインドコントロール論不毛
追記9.冷血
追記10.広い視野?
追記11.学生時代の仏縁
追記12.勝興寺の惨状
追記13.仏恩と師恩
追記14.因果の道理
追記15.マインドコントロール?
追記16.無責任
追記17.あえてよかった
追記18.沈黙
追記19.錯誤相関?
追記20.一向専念
追記21.この程度
追記22.思い込み
追記23.意味のある苦しみ
追記24.二河白道
追記25.生きる目的ハッキリすれば
追記26.急いで急がず急がず急ぐ
追記27.ご恩を有難く感謝する者
追記28.光に向かって
 「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
「親鸞会はマインドコントロールをしているのではないか」という批判を論破するサイト。
マインドコントロールとは何か、そして、親鸞聖人の教えはいかなるものか、他力の信心とは何なのか、詳しく解説しています。
オススメです!
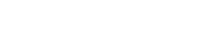
平成19年度下半期の芥川賞を受賞したのは、31歳の川上未映子(みえこ)さん。
川上さんの実家には、一冊も本がなかったというから驚きです。
子供の教育に力をいれる親ではなく、文学に関する英才教育はゼロで、文学に関心を深めたのは10代後半になってから。それも、国語の教科書で文学に触れたのだそうです。
ついつい
「うちの親には教養がないから」
「学校の先生が悪かった」
などと、環境のせいにしがちな自分を反省させられます。
環境はあくまで「縁」であって、「因」は自分の種まきによるのですから。努力、努力。
「幼いときはどんな子供でしたか」
という問いに、
「一見、大阪らしい調子乗りなんやけど、そのくせ
『なんで人は死ぬんだろう』とか考えている面倒くさい子だった。
こどもは身近な人が死ぬと、しばらくの間、夜中に起きては
『あ、私もいつか死ぬ』と怖くなったりしますよね。
あの感情って、普通はしばらく経つと忘れるのに、私はおじいちゃんが死んだ後、
かなり長い間、しつこく持っていたんです」
と答えています。
死について敏感な感覚をお持ちのようですね。
「無常を観ずるは菩提心のはじめなり」
死(無常)から目をそらさず、まっすぐに観ていくことが本当の幸せ(菩提)につながると言われますが、死に鈍感になりたくはないもの。
また、
「私、生は苦なり、生きていくことは基本的にしんどいものだと思っているんです」
とも語っています。
「人生は苦なり(Life is suffering.)」
とは2600年前、インドで活躍された、お釈迦様の言葉。これは古今東西変わらぬ真理です。
●さらに川上さんは、次のような告白もしています。
「自分の中に言葉にできないような不安や問いがあって、それを、本を通して考えたかったんです」
考えさせますね。
「言葉にできないような不安」
さて、一体これは何でしょう。
あの芥川龍之介が、自殺直前に動機として述べた「ぼんやりとした不安」に通じるものがあるかもしれません。
さすが芥川賞作家。
この「ぼんやりとした不安」とは、仏教でいう「無明の闇」の影ではないかと、複数の人が指摘しています。
「無明の闇」とは、「後生暗い心」とも言われ、「死んだらどうなるか分からない心」。仏教で、苦しみの根元とされる心です。
私たちの心の奥底にひそんでいますが、ほとんどの人は、まったく自覚していない。日常の忙しさ、目先の楽しみ、あれやこれやにまぎらわせて気づかないのです。
しかし、何をしていても、何を手に入れても、金も地位も名誉も人間関係も、望みうるすべてがかなえられても、私たちの本心は少しも喜んでいません。人として生まれてきた歓喜を知りません。
いつも、得体の知れない不安に包まれています。ただ、ぼんやりしています。これは、臨終に、まっ暗がりとなって知らされます。無明の闇が、眼前に突きつけられるのです。
この心がどのようなものか、について、おそらく親鸞会ほど、くわしく教えてくれるところはないでしょう。
・無常
・人生は苦なり
・無明の闇
川上未映子さんは、とても仏教的な方のような気がしています。親鸞会館のご法話に参詣されたら、きっと、その「言葉にできないような不安や問い」の正体が、おわかりになることでしょう。
無論、その解決も。
※資料 芥川賞受賞後 新聞各紙掲載記事より
「服と違って体は脱げない。成長というか衰退というか、時の経過を余儀なくされるものを書けないか、と考えました。」(朝日新聞 ひと)
大阪で育った子ども時代は家が貧しく「なんで生きているだろう」と思った。1歳年下の弟の学費を稼ぐために高校卒業後ホステスになる。声帯ポリープのため入院したとき、「自分とは何か」を知りたくて、ベッドで埴谷雄高の小説「死霊」を読みふけった。(読売新聞 顔)
「乳と卵」は大阪から上京した母娘と東京の叔母との夏の3日間を描く。豊胸手術を希望する母。初潮を迎える娘は大人の仲間入りする不安におののきしゃべらなくなる。母と娘、卵子と精子を対比的に構成し、生きる意味を根源的に問う意欲作だ。(毎日新聞 ひと)
「『私』の問題を突き詰めて、物語として浮き彫りにしたい。今回は私が女だから女の子とを書いただけで、基本的には人間について書いているつもりです」(北日本新聞 けさの人)